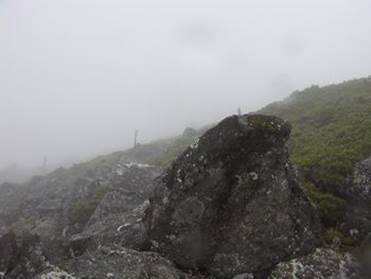|
|
|
|
|
|
乗鞍岳 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2002年 9月21日 阿多野コース往復(単独・日帰り) |
|||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<ツリフネソウ> |
|||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
5:45 自宅出発 6:50 営林署ゲート着 ここから乗用車でも入れるような林道を登山口まで歩くことになるが、土砂崩れの所や路側が不安定な所もある。 途中、黒谷の冷たい水が道路を横断して流れているので、ここで飲料水の補給ができる。 7:50 登山口着 ここからは、雑木林の間を一気に尾根まで登っていく、途中木々の間から御岳が壮観な顔をのぞかせる。 尾根からは林間のゆるい登山道が森林限界まで続く。 10:00 森林限界 ここからは這い松が生い茂ってやや不明瞭な登山道となる。 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
<不明瞭になりつつある登山口> |
|||
|
7:50 登山口着 ここからは、雑木林の間を一気に尾根まで登っていく、途中木々の間から御岳が壮観な顔をのぞかせる。 尾根からは林間のゆるい登山道が森林限界まで続く。 |
|||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
<鬱蒼としたシラビソの林の中> |
|
<森林限界を超えたあたり> |
|
|
<登山道の様子> |
|||
|
10:00 森林限界 ここからは這い松が生い茂ってやや不明瞭な登山道となる。 |
|||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
<中洞権現> |
|||
|
乗鞍青屋登山道と上牧太郎之助 江戸時代の安政6年、 朝日町の青屋に上牧太郎之助という人が生まれた。 登山が好きだった太郎之助は、 山岳信仰と千町ケ原の美しさに取りつかれ、自ら乗鞍までの登山道をきり開く決意をした。 明治29年から活動を開始し、多くの有志と理解者からの寄付と労働力の提供を受けて約40年の歳月をかけて、 昭和8年に全通させ た。 青屋地区の入口から山頂までの88ヵ所に2体ずつ登山道の目印として石仏を設置した。 この登山道の安全祈願には鎌倉円覚寺の朝比奈 宗源師があたった。 あの頃のことだから、大変な事業だったろう。 月日が経って、新しい登山道が別の場所に作られると、この道を使う人がほとんどなく、荒れ果てていった。 平成13年、先祖の偉業を惜しみ「乗鞍青屋登山道復興する会」が地元の有志で結成され、草払いや、石仏の発掘などをし、平成15年 に道の復興を遂げた。 この活動は5年続いたが、高齢化の理由から現在は会としての活動は中止している。(岐阜ブログから引用させていただきました) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<???> |
|
<登山道脇に安置されていた地蔵さん> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
<山頂が見えてきた> |
|
<エコーラインも> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
<非難小屋と綺麗な内部> |
|||
|
12:40 山頂 今回も結構人が多くて、山頂神社付近は銀座状態、またスカイラインを見るとものすごい数の車が渋滞していた。 ぼちぼち紅葉が始まったようである。 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|